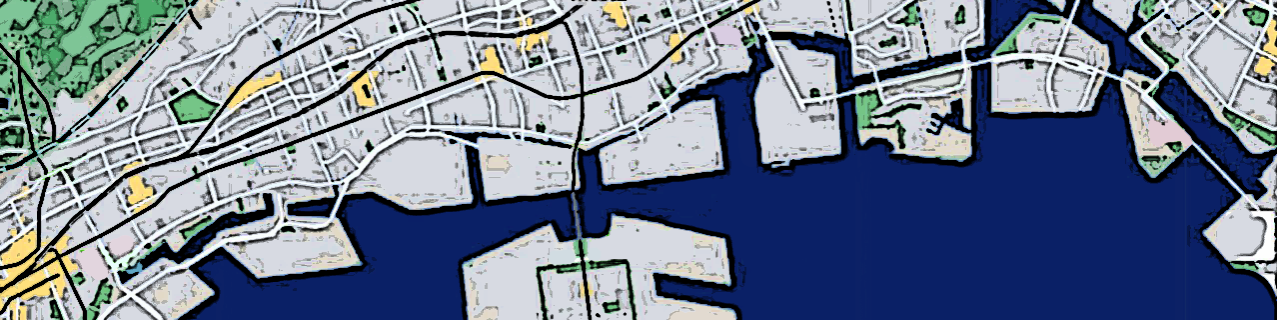イザナギ・イザナミが国産みの前に降り立った場所「おのころ島」の比定地は淡路島内だけでも複数あり、和歌山県の友が島など他県にも及んでいます。ナギ・ナミという海洋的な名前の神様は、皇祖神アマテラスの祖神とされるまでは単に淡路島を中心とする「海人」たちの奉じる一地方神であったのが、とくに「ワケ王朝」と呼ばれる応神天皇以降に御食国として宮廷に食べ物を供給する中で、淡路島の神様への感謝や畏怖の念が王族にも浸透していったのではと考えられています(※1)
おのころ島の存在も、ポリネシアなどの海洋民族が「原古の岩」信仰を持っていたのが淡路島にも伝わって、あの島がそうだよ、と定着していったのではないかとされますが、ではそれがどの島だったのかは明確ではないのです。
その中でも有力候補なのが、淡路島の4.6km南に位置する小島の「沼島」です。理由のひとつが、下の上立神岩の存在。沼島の東側海岸べりにそびえる奇岩が、天地創造に使われた「天沼矛」の先に似ています。

上立神岩
イザナギ・イザナミが最初に産んだ蛭子・淡島が足が立たないので流されたという記述は、彼らが天照大神の兄だったというのが一般的なとらえかたですが、淡路島の兄、つまり島として成り立たなかった浅瀬が淡路島の周囲にあって、それを説明するためだったというとらえかたもあります(※2)。今も浅瀬の多い瀬戸内海なので、その考え方の方が幼児の島流しよりしっくりくるのではないでしょうか。
海に浮かぶ島とさらに小さい島や浅瀬、それらの成り立ちについてあれこれ考えた古代の人々の想像力や創作力に魅せられます。

沼島行きフェリー
沼島へ行くには淡路島本島からフェリーに乗ります。本島の土生港から一日10便の往復で、所要時間約10分。夏の鱧料理が有名で、鱧を食べに沼島へ行くのを毎年楽しみにしている方がたくさんいるのです。
港から湾沿いに10分ほど歩くと「おのころ神社」があります。本島にあるのは「おのころ島神社」ですが、沼島のこちらは島がつきません。漢字で「自凝神社」と書かれていました。



長い石段を上ると、ひっそりした本殿の奥にイザナギ・イザナミ像があります。おごそかな気分に包まれるいい神社です。この神社の存在も「沼島こそおのころ島である」という主張の根拠になっています。
このおのころ神社と上立神岩を見て、鱧を食べてもじゅうぶん日帰りできますが、本島側の港も便利な場所ではないのでその移動も計算に入れなければなりません。島内にはいくつか料理旅館や民宿があるので、泊まれば本島以上に「島時間」が流れる雰囲気を存分に味わえると思います。
上記の観光サイトにも記載がありますが、沼島といえば歴史小説に登場する沼島衆や沼島水軍などの優秀な船乗りたちも有名です。とくに司馬遼太郎が、淡路島出身の高田谷嘉兵衛について書いた「菜の花の沖」で、世界中で小島の住人は多いが、沼島衆ほどに気概と高い能力をもっていた海の民は、まれなのではないか」とまで語っています。
そんな背景を知らずとも、島は小学校等の建物も立派ですし、公共トイレもきれい、観光用の遊歩道も整っていて、島の人たちの気概が感じられます。ぜひ一度は訪れてほしい島です。
※1 松前健「日本の神々」 1974年9月
※2 宮坂光次「蛭児説話の起因と其変遷」(加藤玄智編『日本文化史論纂』中文館書店、1937年11月)